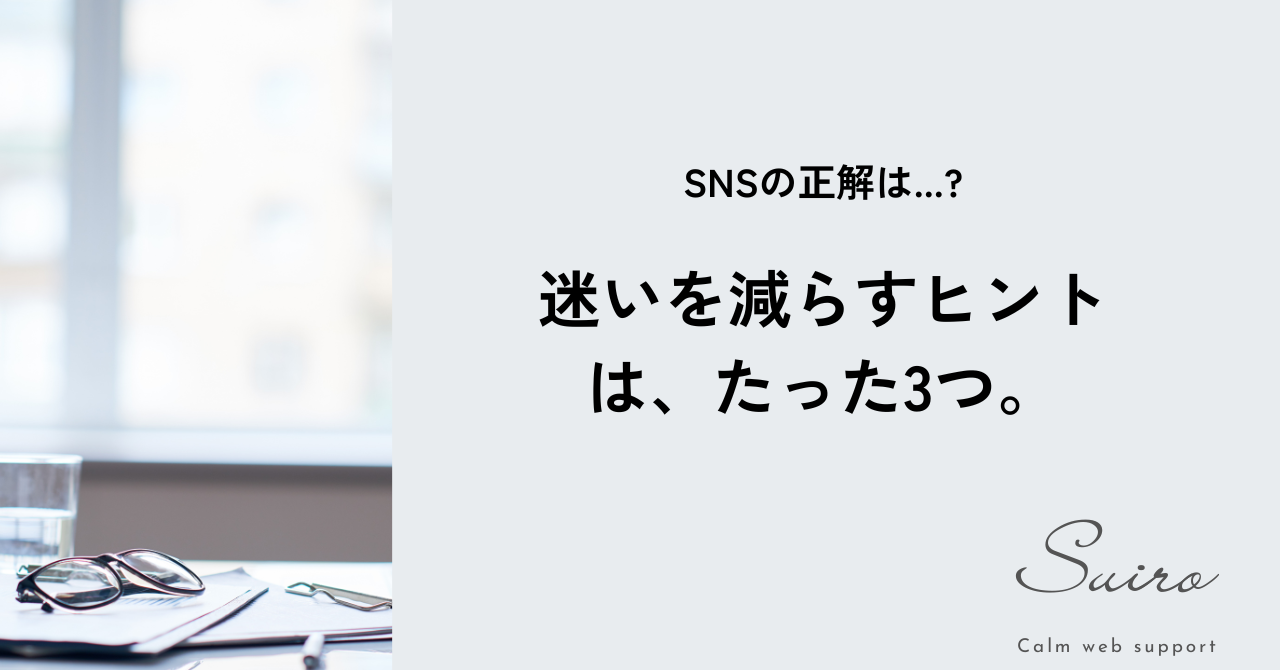前回の記事では、「SNS投稿の正解が見えないときに起こりやすい失敗パターン」についてお話ししました。
今回はその続編として、投稿で見直したいことついてご紹介します。
わたしも会社のSNSを担当してきて、「正解が見えない」と思うことが何度もありました。
投稿して反応が薄いと、「これで合っているのかな?」と不安になったり。
そんな状態では、心のこもった文章も書けないし、誰かに届いているという実感もない。
そこで気づいたことがありました。
それは、文章を書くときの土台となる視点を整理することの大切さです。
この3つを明確にすることで、投稿への迷いが減り、「誰に何を書くのか」という方向性も見えてきました。
発信するのが苦手と感じたときに見直す「3つの視点」
誰に届けたいかを決める
SNSに限らず、まずは誰に向けて書いているかがはっきりしていないと、どんなにがんばって投稿しても反応が安定しません。それは届けたい相手に届いていないからです。
たとえば、若い世代に向けているのか、家族層なのか、法人なのか。
相手が違えば、投稿内容、写真の選び方、言葉のトーンも変わりますよね。
ある会社のInstagramでは
「全国のたくさんの人に見てもらいたい」
「バズを狙いたい」
という思いで投稿していました。
まず対象が広すぎると、統一感がないのでアカウント全体がまとまりません。
バズを狙うのは悪いことではありませんが、一時的に数字が増えてもファンになってくれる人や継続的に見てくれる人は少ないのが実情です。
それよりも、会社やお店に興味を持ってくれる人に向けて、ていねいに投稿を重ねることが大切です。
「読んでほしい人」を具体的にイメージすると、文章や写真、全体のトーンにも統一感が出てきます。
結果としてフォロワーや表示回数がじわじわ増えていき、問い合わせやコメントといった次の行動にもつながります。
たとえば、飲食店のInstagramアカウントで、お店のサービス(ランチ)について紹介するとします。
同じ“ランチ投稿”でも
・若い女性に向けるなら「映える写真+気分を上げる言葉」
・家族層に向けるなら「安心感・雰囲気・居心地」を伝える言葉
が合います。
なんとなくランチ内容を紹介するのでは誰にもささりません。
ターゲットによって同じ内容でも見せ方を変えれば、反応も変わります。
相手の“困りごと”に寄り添う
商品の宣伝やサービス紹介だけでは、なかなか読んでもらえません。
「お客さんは何に困っているのか?」を考えると、投稿の切り口が明らかに変わります。
たとえば飲食店なら
といったニーズが考えられます。
こうした困りごとに応える投稿をすれば、読み手が「自分のための情報だ」と感じてもらいやすくなります。
伝えたい相手に、どう伝えるか
伝えたい相手と目的を決めたら、ここでやっと見せ方を考える段階になります。
誰に何を届けたいのかはっきりすると、写真や文章のトーン、選ぶ言葉まで自然と変わっていきます。
フォロワーに安定して読んでもらいたいなら、1つのアカウント内での投稿は、パターンやイメージを統一するのがおすすめです。
SNSはテクニックよりまず土台を整える
SNSの投稿で反応を感じにくいときは、テクニックよりもまず「土台」を整えることが大切です。
もし何を投稿したらいいかわからない、というときは、会社のホームページやパンフレットを見返してみてください。お店ならメニューやサービス内容をもういちど確認してみてください。
SNSが苦手でも、伝えたい思いがあるなら大丈夫です。
迷ったときは「誰に・何を・どう伝えるか」を思い出して、少しずつ整えていきましょう。
*今日の振り返りメモ*
投稿ごとに「誰に届けたいか」を考えてみる。
1投稿1目的で“何を伝えるか”を整理する。
色や言葉など「どう伝えるか」を揃えていく。